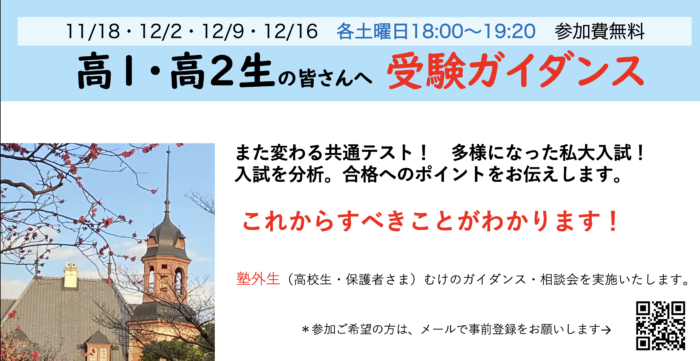古文の読解、まずは主語の特定からやっていきましょう!
国語担当:桝崎 徹

古文は現代語から比べると、いろいろなものが省略されています。現代の日本語自体にもいろんな省略がありますが、慣れない古文では、主語が現代語以上に省略されているので、話が全然見えなくなってしまうことがあり、高校生にとっては難しく見えてしまいます。
たとえば、
今は昔、竹取の翁といふものありけり。~ 『竹取物語』
有名な竹取物語の冒頭ですね。「これくらい大丈夫やん」と思われるでしょう。でも、この中にも省略はあります。「竹取の翁といふもの」と「ありけり」の間に、“が”という、主語を表す大切な助詞が省略されていますね。・・・現代の日常会話でもこのまま話す人が多いのですが・・・。
このように、古文の勉強で、注意すべき省略はいろいろありますが中でも特に注意しなくてはならないのが、「主語の省略」です。
・・・主語が省略されていても気にならへんし・・・という人が最近は多くて、これはなかなか現代文にも影響してきて大変ですねんけど・・・それは置いといて。いや、ホンマに笑い事ではないんですけどもね。
“誰が、何をしたのか”は重要なんです。現代文でも古文でも。そこで主語を補足しながら読んでいくことが大切になってきます。ここは、古文の勉強法でまず注意していただきたいポイントです。
それでは、なぜ主語が省略されるのか?―――書かなくても分かるからなんです。当たり前すぎますが。これは古文だけの話ではなく、日本語がそうだからです。
例えば、桝崎というその頃は純情であった青年の日記があるとします。その日記の中に、
“今日は想いを伝える日だ。校門前の神社で「好きです」と言ったら、「ごめんなさい」と走り去った。”
このような描写があったとします。・・・哀しいですが。さて、この「言ったら」と「走り去った」という述語の主語は省略されてますね。誰が「言った」のか誰が「走り去った」のか、書かれていません。でも主語は――桝崎が「言った」で、言われた方が「走り去った」ですね。なぜわかるのか?それはわざわざ書かなくても分かるからですよね。作者と読者の間に、「言わなくても(書かなくても)絶対理解できるだろう」という了解があるからなんです。
それでは古文の話です。

☆「て、」「で、」の前後の主語は、ほぼ同じ
まずは「て、」
~(右大臣殿は)我、行きて試みんとおぼして、日の装束うるはしくして、檳榔の車に乗りて、御後前多く具して、集まりつどひたるものどものけさせて、車かけはづして、榻をたてて、~『宇治拾遺物語』
“[現代語訳]~(右大臣殿は)私が行って試してみようとお思いになって、束帯をきちんと見事に着て、檳榔の車に乗って、随従者と前駆の者をたくさん引き連れて、そこの集まっている者たちをのけさせて、牛につないである車を外して、車の轅を乗せる台を立てて、~”
この「て、」の前後の主語は全部「右大臣殿」ですね。もしか別の主語が出てきたら、書かれているはずです。逆に、書かれていないということは、そのままでいいんです。これは現代語の
「桝崎が朝起きて、歯を磨いて、顔洗って、頭剃って、~~」
と同じなんです。・・・毎朝、剃ってるんです。毎朝、御髪おろしています・・・。この頭をキープするのも大変なんです。・・・それはいいとして。あ、この時も、もしか、「頭剃る」のが別の人なら、きっちり書いていないと分かりませんよね。
次は「で、」
~親王、大殿ごもらで、明かしたまうてけり。~『伊勢物語』
“[現代語訳] 親王は、お休みにならないで、夜をお明かしになってしまった”
この「で、」の前後の主語も同じ「親王」のままですね。
ただ、この「で、」には注意が必要です。それは訳し方です。先ほどの「て、」は現代語と同じで「・・・て、」でいいのですが、「で、」は「・・・ないで」というふうに打消で訳してください。
※「て、」の注意点!
主語は変わらないのですが、先ほどのようにずっと「て、」で並列に並べられている場合(縦書きで、すぐ下に修飾していっている場合)はいいのですが、下の文のような場合、
~(舎人は)いと悪しき事なりと腹立たしうて、まうとは、いかで情なく、幼き者をかくはするぞといへば、~『宇治拾遺物語』
直下にかかると見てしまうと、
「腹立たしうて~かくはするぞ」となりますが、おかしいですよね?
「腹立たしうて「~~」といへば」と「いへば」にかかると見ればいいわけです。
つまり、会話文をはさむと係りどころがとぶというわけです。
これは「 」を省略する(※正確にいうともともと「 」なんて記号や決まりはないんです。)文章では、死ぬほどあるパターン。
ちなみに現代語訳はこうなります。
~(舎人は)とても悪い子だと腹を立てて、「おまえは、どうして情け容赦もなく幼い子供に何という事をするのか」と言うと、~
さて、ここまで、主語が変わらない可能性が高い、「て、」「で、」を主に見てきました。(今回は紹介しませんでしたが、これに「つつ」「ながら」を加えてもらってもいいです。)
続きまして、“主語が変わる”バージョン、お送りいたします。もちろん、これも100パーセントではありません。主語が変わる可能性の高いもの、変わるかもしれない目印、だと思ってください。
☆主語を変える代表格「を・に・が・ど・ば」
「を・に・が・ど・ば」って何?
まずは、簡単に「を・に・ど・ば」について、説明しましょう。これらの助詞を見つけて、主語の変わり目を見つける昔ながらの読解法のことです。
鬼と会ったら切る(を・に、を見つけたら、文を切る)とか
ドーバー海峡(ど・ば、の間には切れ目がある)
漢文では、「鬼と会ったら帰る」なんていう風に教わることもあるかもしれません。目的語が下にあるからですね。
さて、この裏側には、「係る所を探す」というものもあります。それが、上記に書きました、
「て・で・つつ・ながら」です。
これらは、逆に切れないよ、係るところがあるよ、どこに係るか探してね、っていうサインです。こうした単純作業をする必要があるんですね。
☆「を・に・が・ど・ば」は、主語が変わる「かも?」と思う。
まず、「を・に・が・ど・ば」です。
これらを見つけたら、主語が変わるかも?
と思ってください。絶対に変わる、ではないですよ。変わる可能性があるから疑って!です。たとえば、
『桝崎、ブサイクなれば、もてず。』(桝崎はブサイクなので、もてない。)
とくれば、主語は変わりませんね。でも、
『桝崎、「〇〇」といへば、笑ふ。』(桝崎が「○○」と言うと、笑う。)
の場合、笑っているのは、桝崎ではないですよね?こういう時には主語が変わっているわけです。だから、「を・に・が・ど・ば」を見つけたら、「主語が変わるかも?」と考える必要があるわけですね。
えっ、説明になってない?それじゃあ、変わるか変わらないかわからないじゃないか!もっと、はっきりと教えてほしい!そりゃそうです。もう少し説明していきますね。
そもそも主語の省略が起こるのは自明だからです。書かなくてもわかるから主語を省略する。よく「古文は主語を省略する」なんてのをみますが、うそです。正しくは、「日本語は」ですね。だから、本来、ぼくらの感覚からすれば、主語は補えるはずなんです。
では実際に注意すべきパターンで勉強しましょう。
☆『言へば笑ふ。』 客体をとる動詞の後は、その客体が主語
まずは、このパターンを考えて見ましょう。
『言へば、笑ふ。』
です。誰が笑うのでしょうか?それは「言われた人」です。なぜ?そう決まるか?
「他にいろいろな可能性があるよね。必ずしも言われた人とは限らないよね。」そう言いたいんですよね?
だったら、書かなくちゃ。
「言ったので、笑った」主語がないなら、聞いている人です。
このように、客体をとる動詞(相手を必要とする動詞)+「ば」「ど」が来た場合、次の動詞の主語は、客体(=相手)が基本です。
まだ納得できない?
『桝崎、抱きつけば、怒る。』
そうです。私は「怒る」のは「抱きつかれた人」だと言っています。
たとえば、その子の親とか、先生とか、彼氏とか、怒りそうな人は確かにいっぱいいます。
でも、
「抱きついたので、怒った」という文章で、突然、登場していない「親」とか「彼氏」とか出て来たら、わからなくないですか?その場合、
「抱きついたので、その子の彼氏が怒った」と書かなければ伝わらない。省略したということは、自明だということなんですね。
☆『遊ぶを見る。』 「見る・聞く」など客体をとる動詞の前は、別人。
今度はこのパターン。
『遊ぶを見る。』
です。
この場合は、「遊ぶ」と「見る」の主体・主語は、別人になります。
これは説明した方がわかりやすい。
「見たんです。見たんです。私見たんです。」
「何を?」
「遊んでるのを見たんです。」
「誰が遊んでるの?」
「私が」
「誰が見たの?」
「私です。」
・・・気持ち悪いですよね。なんなの、この人…ってなります。
だから、こういう動詞の前は、別人です。
『~に会う。』も同じですね。
ところが、なぜか生徒はこれが苦手。というのも、ひとつは古文の場合、「~を」「~に」といくときに、
桝崎、(子どもが遊ぶの)を見る
桝崎、(子どもが遊んでいるの)に会う
というふうに、「の」が入らないんです。(※この「の」の省略もかなり大事なのです!) このたったひとつの「の」が欠けるだけで、違う文に見えるみたい。
そしてもうひとつは「を」とか「に」の後には「、」がないことが多い。「、」がないだけで、主語が続くような感覚になってしまうようですね。
「~を」「~に」といくときに、「の」が入らないんです。(※この「の」の省略もかなり大事なのです!) このたったひとつの「の」が欠けるだけで、違う文に見えるみたい。
今回は“主語の特定”について書かせていただきました。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。次回の古文の勉強法は、古文文法のかなめ、古文を嫌いにする第一人者・『助動詞』さんをいかにマスターするかです!
大学受験では、国公立大学受験の人にとっては、文系でも理系でも大学入学共通テストで古文は必須ですし、例えば京大受験する人には、理系でも二次試験で古文は必須です。また、私大文系受験の人にとっては、ほぼ古文は必須になっています。
したがって、こうした大学を志望している人は、しっかり古文の対策をしていきたいものです。
今後、大学受験の勉強法を色々お伝えしていきますので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
国語の勉強の仕方:関連情報
*関連するページを、リンクを貼ってあげておきます。
基礎から国語のルールを理解し論理的に読解する力を鍛える!大学入試現代文の読み方
大学受験・古文の勉強の仕方 その3古文文法を読解につなげる②
#大学受験 #勉強の仕方 #勉強法 #古文 #主語 #LEAD #パーソナルラボ #個別指導
#大学入学共通テスト対策 #国公立大学 #私大文系