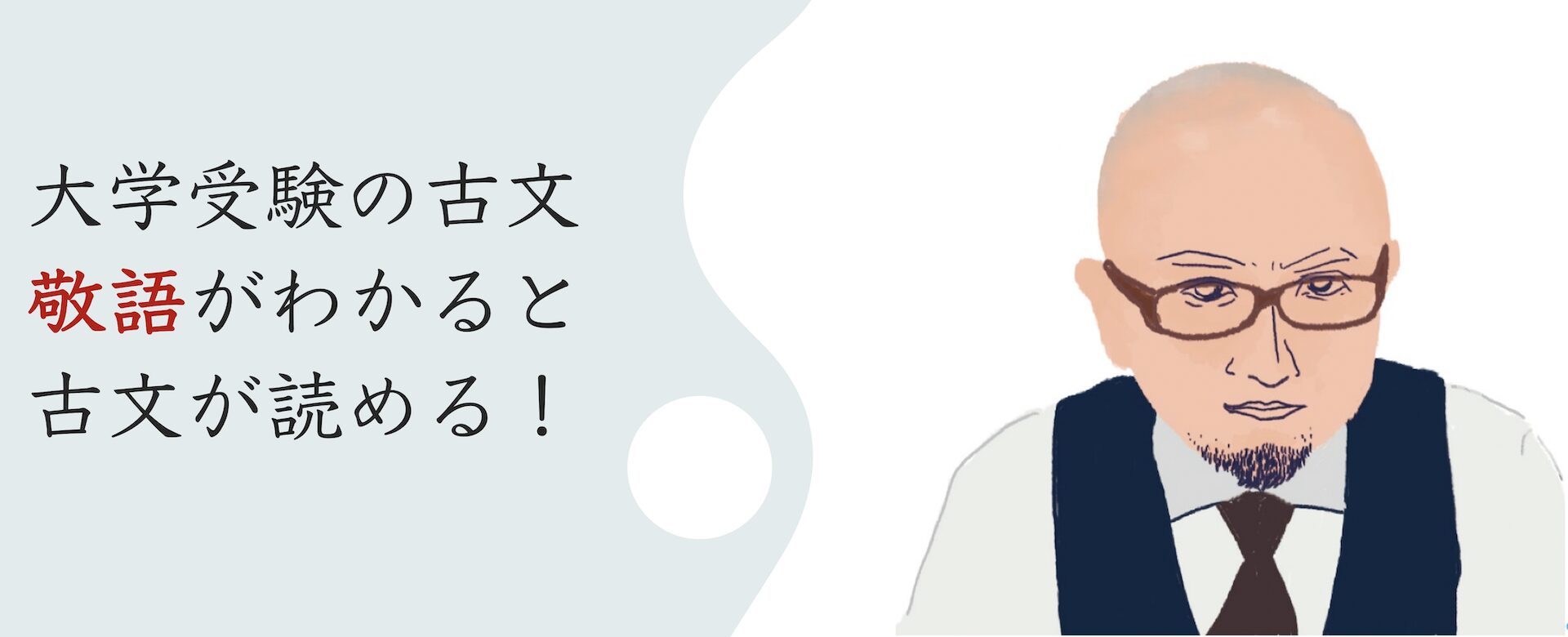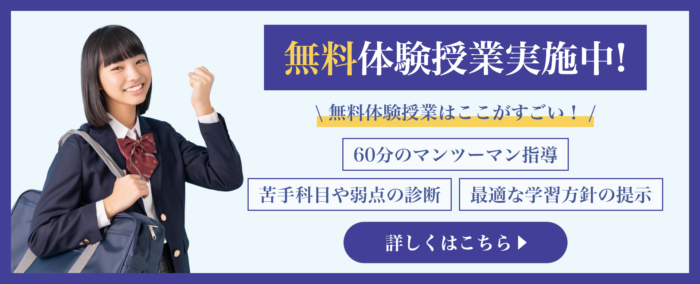おはようございます。こんにちは。こんばんは。大学受験パーソナルラボLEADの国語科:桝崎徹です。
長らくこちらのブログをサボってしまってまして、すみません・・・。(・・・なんか毎回、書き出しがこんな感じになってしもてますが・・・。)
LEADの国語関係のブログは結構読んでもらっている方が多いとのことですのに、ホンマに申し訳ないです。
それで、今回は古文の「敬語」について、つらつら(頭はテカテカ・・・)書いていきたいと思います。できましたら、最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。
今回の内容は、「古文の敬語の具体的な勉強の仕方」に行く前に、「なんで古文の敬語を勉強していかなアカンのか?」、「なんで敬語が苦手な人が多いのか?」を中心に書かせてください。(※「具体的な勉強の仕方」については、次回に書かせてもらいます。)
だいたい、そもそも、古文という科目について、特に苦手な生徒さんの口癖は「なんで昔の文章とか単語とか、そんなんやらなあかんのよぉ~‼」ですから、「古文の敬語」なんか、その最たるものです・・・。
それでは行ってみましょう~‼

現代語の敬語
古文の敬語について始める前に、まずは現代語での敬語について確認していきましょう。敬語の使われ方は現代も古文の世界も同じです。変わりません。以下のとおりです。
① 尊敬語…動作の主体(=その動作をしている主語)に対して敬意を表す言い方。
② 謙譲語…動作の受け手(=その動作を受ける対象。目的語。)に対して敬意を表す言い方。
③ 丁寧語…聞き手/読者に対して敬意を表す丁寧な言い方。
・・・ちょっと、なんかいきなり参考書のような文言を並べてしまいましたが、内容は
簡単です。
①の「尊敬語」はわかりますよね。
(例) 校長先生が、全校朝礼で「トイレでタバコを吸わないように‼」とおっしゃった。
とかですよね。(素敵な学校です‼(笑))この場合、「おっしゃる」という動作をしている「校長先生」を高めている(敬意を払っている)言い方ですな。
②の「謙譲語」については、「自分を下げて相手を高める」とか、「へりくだった言い方」
とか、まぁいろいろあってそれはそれで正しいんですが、そんな難しく考えないで、ここはもう単純に「動作の受け手を高める言い方」と考えてください。
(例) 平社員の桝崎が、取引先の矢沢専務に、お電話差し上げる。
とかですね。この時、「お電話差し上げる動作」をしているのは、「平社員の桝崎」ですが、敬意は、その「お電話を差し上げる動作」を「受けている」、「矢沢専務」ですね。
➂の丁寧語は、
(例) (小学3年生の桝崎君の日記より)
5月31日(金) 今日僕は動物園に行きました。受付でキレイなお姉さんが「おはようございます。」と言ってくれました。うれしかったです。
この日記の中の、「行きました。」の「ました。」と「うれしかったです。」の「です。」は、この日記を読んでいる人(=読者)に対して丁寧な言い方をしてますね。また、受付のキレイなお姉さんの「おはようございます。」の「ございます。」は、「キレイなお姉さん」から、その言葉を聞いている(=聞き手。この場合は作者の「僕」)人に対しての丁寧な言い方になっています。
なんで敬語が苦手な人が多いのか?
はい。これまで、「現代語の敬語」について書きましたが、皆さん、どうですか?普段、ちゃんと意識して敬語を使ってますか?・・・ほぼ、「タメ語」とちがいますか?・・・そうでしょうなぁ。(-_-;)
そうなんです。そのあたりのところが、古文の敬語が苦手な人を作っている大きな要因でもあるんです。以下に続きます。

現代社会と古文の社会は違う‼
現代は、「身分の格付けがない社会」ですよね。基本的に。(いろんなところで「格付けランキング」なんていう言葉がありますけども、「身分」での格付けはありません。)
ところが、古文の世界は、「官位社会」です。言い換えれば、「めちゃくちゃ格付けがある社会」です。正三位より正二位の方がエラくて(身分が高くて)、それよりも正一位の方がエラい、という社会。ですから、敬語がないと、生きていけないんですね。
そういう制度的な違いが明確にある。現代なら、単語だけで相手に通じてしまいますからね。(・・・本当はこれではいけないんですが・・・。)
だから皆さんも日常生活において、それほど敬語を意識していない。だからうまく使えない。
変な敬語に気づけますか?
普段から敬語を意識して使っていない学生が、学校を卒業してからいきなり社会に放り出されて、敬語を使わなければいけない場面に遭遇する。・・・見てられませんわぁ。
よくあります。そんな場面。この前も家族で回転ずしに行ったんですが、(・・・そんなん、カウンターのお寿司屋さんになんか、行けませんがなっ‼)受付のお兄ちゃんが、「何名様でしょうか?」「三人です。」・・・ここまでの流れはまぁいいとして、そしてでましたわ!「三名様でよろしかったでしょうか?」
・・・今言うたがな‼「~よろしかったでしょうか」って、「かった」って、今やがな‼・・・そんな昔の話しとるか⁉どんだけ前の確認しとんねんっ‼
・・・とは言いませんでしたけどね。
ちょっと話が古文から逸れたかもしれませんが、ちょっと書き手が興奮してしまいましたので、ついでに、以下の、現代の丁寧な言い方のおかしなところ、ちゃんと指摘して、おかしな理由を叙述できますか?いわゆる、「バイト敬語」ってやつです。
(※以下の数行は、ただ単に、書き手の興奮度合いを示しているものでありますから、ご興味のある方だけ、お読みください。ただ、「ツッコミ」の考え方の訓練にはなります。)
⑴「こちら、お釣りになります。」
⑵「ご注文の方(ほう)は、お決まりですか?」
LEADの授業で古文の敬語については学ぶとき、時々、上記の質問を生徒さんに向けてする時がありますが、だいたいみんな、「別に普通・・・」とのたもうてくれます・・・( ;∀;)
⑴の「お釣りになります。」は、多分、「物事を断定しないことがいい」というような日
本の文化的な背景やら、「お~になる」という尊敬語(例、「帝(みかど)が、お聞きになる」から来てしまったものなのかもしれませんが、「お釣りになる」て・・・ほんだらこれはお釣りと違うんかいなっ‼ってツッコまなければアカン状況ですねんで、ホンマは‼「今はお釣りではないけども、待ってたらいつかこれは「お釣り」というものになるんかいなっ‼」と。「彼は一生懸命勉強して、やがてお医者さんになった。」みたいに‼
それとも、伝統芸能の世界でよくある、「襲名」みたいなもんかいなっ‼上方落語の爆笑王・桂枝雀師匠が、その前の高座名が桂小米さんで、そのころは正統派的な端正な落語をやってはったけども、枝雀に襲名なさってから型破りな爆笑型の落語に変えはったみたにかいなっ‼
それともあれかいっ‼魚で言うところの「出世魚」かいなっ‼ハマチがメジロになって、
ブリになるようなもんかなっ‼まぁ、これは関西と関東で若干の違いはあるようやけど・・・、・・・いや、そんな話ちゃうねんっ‼
・・・くらいのツッコミは必要になりますわな。(息継ぎナシで)
⑵はどうでしょうか?
「ご注文の方(ほう)」の「方(ほう)」っ‼二つあるうちのどっちか一個の方(ほう)かいなっ‼「背の高い方と低い方」とか「中川家のお兄ちゃんの方」とかの「方(ほう)」かっ⁉ほんだら、「ご注文」と「ご注文ではない」二つのモンがあって、そのうちの「ご注文の方」になるがなっ‼
それとも何かいっ‼「あっちの方に行ってもらいましたら、コンビニがあります。」の「方(ほう)」かっ⁉ほんだら、「ご注文の方向」があって、注文をいまここでしたいのに、わざわざ「ご注文のところ」までいって、ほんでからここまで戻ってきて、ご注文をしやなあかんのかいなっ‼(これも息継ぎナシで)
・・・以上、現代語の変な敬語についての、書き手のストレスの発散でありました・・・。
それでは現代語の敬語にすら十分に使いこなせていないのに、なぜ、古文の敬語までやらなくてはいけないのか?
以下に続けます。
なぜ古文の敬語をやらなくてはならないのか?
・・・ちゃんと古文の世界に話を戻します。
古文は、めちゃくちゃ主語を省略する言語です。(この点につきましては、以前のブログでも書きました。)古文に限らず、現代語の日本語もそうですよね。いちいち主語を付けない。それに対して、英語は全く違いますね。英語は「自分の言いたいことを、論理を駆使して相手に理解させる言語」なので、主語の省略なんて、ありえない。「誰が、いつ、どこで、何をした」かを明確に伝える言語です。
日本語は全く逆です。多分、「明確にしないこと/隠すこと」をいいとする文化があるんでしょうね。だから、助動詞にも「婉曲」という意味の助動詞がある。英語なら考えられないような。そのあたりのところが、「奥ゆかしさ」なんでしょう。
だから、「主語」ですらも省略する。「言わなくても相手にわかるであろう」ことは言わないし、書かない。
そんなことをされると、困るんです。現代語ならまだ何とかなるかもしれませんが、そんなことを、古文でされてしまうと・・・。
はい、そんな時に、敬語を見なけれないけないんです。敬語を見ると、その文の主語が分かるんです。

敬語が分かれば、省略されている主語が分かる‼
はい、以下の古文を読んでみてください。『枕草子』からです。
「 雪のいと高う降りたるを、例ならず御格子まゐりて、炭櫃に火おこして、物語など
して集まりさぶらふに、「少納言よ、香炉峰の雪いかならむ。」と仰せらるれば、御格
子上げさせて、御簾を高く上げたれば、笑はせたまふ。~(後略)~」
(現代語訳)
「 雪がたいそう高く降り積もっている時に、いつもと違って御格子(みこうし)を下ろ
し申し上げて、いろりに火を起こして、世間話などをして集まって、お仕えしている
時に、「少納言よ、香炉峰の雪はどんなだろう。」とおっしゃるので、御格子を上げさ
せて、御簾を高く巻き上げると、お笑いになる。」
はい。この文章、始めの「雪の」(雪が、)以外、主語が全く書かれていませんね。つまり、「誰が、何をした。」の「誰が」が一切ないんです。・・・迷惑な話です・・・。
これを正しく理解するには、まず、「文学史の古典常識」が必要になってきます。今回の場合、『枕草子』なので、筆者は「清少納言」。それから清少納言がお仕えしていた人は「中宮定子」である、ということ。

ちょっと見ていきましょう。
「(現代語訳)雪がたいそう高く降り積もっている時に」、誰が「例ならず御格子まゐりて、/炭櫃に火おこして、/物語などして集まりさぶらふに、」していたんでしょうか?
この時、「御格子まゐる」が謙譲語で、「小窓を開け申し上げる(閉め申し上げる)」
と訳さなければいけないこと、「さぶらふ」が本動詞の謙譲語の場合、「お仕え申し上げる(エ
ライ人のおそばに控える)」と訳さなければいけないこと、等は覚えなくてはいけないこと
です。ただ、細かなことは、次回以降にやっていきましょう。
答えから言いますと、主語は「筆者(=清少納言)」です。
「(現代語訳) 雪がたいそう高く降り積もっている時に、(私が)いつもと違って御格子(みこうし)を下ろし申し上げて、(私が)いろりに火を起こして、(私が)世間話などをして集まって、(私が)お仕えしている時に、」が直訳です。(※“「て」と「で」の前後では主語は変わらない”ということは、以前にもやりましたね‼逆に、主語が変わる可能性の高いものは「を・に・が・ど・ば」の時でした。)
さて、その後の「「少納言よ、香炉峰の雪いかならむ。」と仰せらるれば」の主語はどうなんでしょうか?誰がそれを仰ったのか?
まず、「集まりさぶらふに、」の「に、」で主語が変わっているのではないか?と予測できた人はなかなかいいですねぇ~‼先ほどの「を・に・が・ど・ば・」の「に」です。そうです。ここで主語は確実に変わっています‼なぜなら、「「少納言よ、香炉峰の雪いかならむ。」と仰せらるれば、」の「仰せらるれば、」の「仰せ」は本動詞の尊敬語。「らるれ」は、尊敬の助動詞だから、主語はエライ人、なんです。(※このように「尊敬語」+「尊敬の助動詞」の組み合わせを「二重尊敬」と言います。だから主語はめちゃくちゃエライ人‼)
この部分の主語は、清少納言がお仕えしていた、「中宮定子」です。「中宮定子」には尊敬語が使われている、ということが分かります。また逆に、この文で尊敬語が使われている動作の主語は中宮定子だ、と考えなければいけないんです。
そしてその後、「~御格子上げさせて、御簾を高く上げたれば、笑はせたまふ。~(後略)~」
と続くのですが、先ほどの「仰せらるれば、」の「ば」でまた主語が変わる‼「~御格子上げさせて、御簾を高く上げたれば」までには尊敬語が使われていないので、主語は「普通の人(=清少納言)」になる。
そしてまた、「笑はせたまふ」には「せたまふ」という二重尊敬だから、主語はエライ人に変わっている。(※「せ」は尊敬の助動詞+「たまふ」は尊敬の補助動詞。)
今までものをくっつけますと、
「~~(私が)お仕えしている時に、「少納言よ、香炉峰の雪はどんなだろう。」と(中宮定子が)おっしゃるので、(私が)御格子を上げさせて、御簾を高く巻き上げると、(中宮定子が)お笑いになる。」
となります。
いかがでしょうか?
これが、敬語が分かれば、主語が分かる。そこから、古文(文の意味)が分かるようになるということなんです。
主語がわからないと、何について書いてあるかわからないので、古文はチンプンカンプンだったはずです。そこから抜け出して、何について書いてあるかわかってくると、文の内容・イメージが掴めるようになります。(もちろん、それだけでなく、単語、助動詞・助詞、古典常識なども強化していくと、もっと古文が読めるようになります。)

「随筆・日記」の、地の文の主語のない動詞の主語は、筆者のことが多い‼
細かなことは、次回のブログ以降にもやっていきますが、古文のジャンルによって、読み方も変えていかなければいけません。
先ほどの『枕草子』は「日記」や「物語」などのジャンル分けをしますと、「随筆」にあたります。そのことから、表題のように、「随筆・日記」の、地の文の主語のない動詞の主語は、筆者のことが多い‼特に謙譲語の場合‼ということがいえます。
現代語でもそうですよね。たとえば、
「5月31日(金) 今日は映画を観に行った。」
というような日記の文章があるとき、「観に行った」のは誰か?となりましたら、これは確実に、「その日記を書いている人」ですね。逆に、
「5月31日(金) 今日は映画を観に行きなさった。」
というような文章の場合、「観に行きなさった」のは誰か?となりましたら、これは確実に、「その日記を書いている人以外の誰かエライ人」ですね。自分が映画を観に行っているのに、「観に行きなさった」と尊敬語の補助動詞を使い人はいませんね。(※ただ、古文の場合、「ずば抜けてエライ人」なんかは、自分の行動に尊敬語を使うような場合もあるんです。これを「自敬敬語/尊敬」などと言いますが、これまた今後、詳しくやっていきましょう。)
古文の場合、先の『枕草子』の文章のそうですし、『徒然草』の、
「九月二十日のころ、ある人に誘はれたてまつりて、明くるまで月見ありくことはべりしに、おぼしいづるところありて、~~(後略)~~」
(現代語訳)
「九月二十日の頃、(私が)ある人に誘われ申し上げて(お誘いいただいて)、(夜が)明けるまで(私が)月を見歩いていたことがありました時に、(ある人が)思い出しなさった所があって、~~(後略)~~」
「ある人に誘われたてまつりて」の「たてまつりて」は謙譲の補助動詞なので、明確な主語が書かれていませんが、上記のルールから、筆者(=吉田兼好)です。その後の、「~はべりしに、」の「に」で主語が変わる。なぜなら次の「おぼしいづる」の「おぼし」が尊敬語だから、です。
今回もまた長くなってしました。
古文の敬語については、次回以降も続けます。なぜなら、非常に大事な分野だからです。
最後までお付き合いくださって、ありがとうございました。
これで、今回はおわりになります(笑)